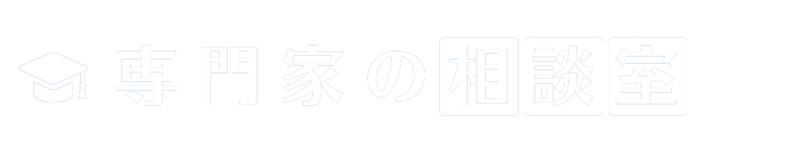フリーランスの方など、個人事業主の中には自宅で仕事をしているなんてことも多いのではないでしょうか。
実は自宅の家賃のうち、事業で使っている比率分は経費として計上することができ、これを家事按分といいます。
今回は、自宅の家賃を経費に計上する方法を徹底解説します。
自宅の家賃を計上することで、経費を増やせるため、大きな節税につながることでしょう。
青色申告での確定申告は必須
まずは、自宅の家賃のうち事業で使っている比率分を経費として計上したい場合には、原則として、青色申告を選択する必要があることを覚えておきましょう。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、白色申告の場合は、家事按分による事業の比率が50%以上でなければ経費とすることができません。
家賃以外も含めて家事按分できる費用は多岐にわたります。
家事按分を使いこなすためにも青色申告の届出を必ず出しておきましょう。
自宅兼事務所の家賃の家事按分計算のやり方は、面積割がおすすめ
実は、家事按分の計算方法は、具体的に決められているわけではありません。
したがって、按分比率は自由に決めてよいのです。
しかし、だからといって、経費を多く計上するために適当な比率を使ってしまえば、税務署に指摘されてしまいます。
そこで、一般的に使われている方法を踏襲して使うのが無難とされています。
自宅兼事務所の家賃の按分割合は、事業に利用している面積の割合を利用する人がほとんどですので、おすすめです。
例えば、3つ部屋があるマンションを賃貸していて、1つの部屋を書斎がわりにしていて、そこは基本的に仕事でしか使っていなかったとしましょう。
一方で、残り2つの部屋はプライベート用に使っている部屋だったとしましょう。
この場合、全面積のうち、書斎がわりにつかっている部屋の面戦の割合を利用することになります。
ちなみに、同居している家族が持ち主である自宅に住んでおり、その家族に家賃を払っているような場合には、一切経費にすることはできませんので、注意してください。
また敷金や保証金は、将来返還される予定のものであるため、家事按分の対象とすることはできませんが、仲介手数料は家事按分の対象にし、経費とすることができます。
一方で、礼金は支払ったままで返還される予定はありませんので、原則、家事按分の対象として経費に計上することができます。
ただし、20万円以上の場合には、賃借期間もしくは5年のうち短い方の期間で按分して計上しなければならないこととなっていますので注意しましょう。
事務所を別に賃貸している場合は、自宅の家賃は経費にできない??仕訳とともに解説
事務所を別に借りている場合でも、自宅に帰って引き続き仕事をしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
実は、このように、事務所はあるけど、自宅でも仕事をしているという場合にも、家事按分して家賃の一部を経費にすることができます。
例えば、基本的には毎日仕事をしていて、月曜から金曜日は事務所で9時から17時まで仕事をし、家に帰ってからも平均4時間は仕事をしているとしましょう。
ただし、土日はほとんど仕事をしていないとします。
自宅の家賃は月20万円。
部屋は3つあり、書斎兼寝室が全面積の20%を占めているとします。
残りの部屋は一つは完全にプライベート用の趣味部屋で全体の30%を占めており、もう一つは共用スペースで全体の50%を占めているとしましょう。
さて、この場合、自宅の家賃20万円のうち、いくらを経費とすることができるでしょうか?
まずは、一日の24時間のうち、平日の4時間は仕事を利用しているわけですから、1週間単位でみると、自宅で仕事をしている時間の割合は、
(4時間×5日)÷(24時間×7日)=約12%
となります。
次に、自宅のうち事業に必要な面積を算出します。
書斎兼寝室が全面積の20%
共用スペースの50%を除いた面積に占める書斎兼寝室の面積の割合は
20%÷(100%-50%)=40%
また、共用スペースも業務上必要な部分も、この40%であると考えることができます。
自宅の家賃月20万円のうち、自宅で仕事をしている時間、その自宅のうち仕事で必要な面積の掛け合わせで家事按分をしてみましょう。
20万円×約12%×40%=約1万円
結論として、月20万円の自宅家賃のうち、月1万円を経費として計上することができると考えられます。
これを仕訳にしてみると以下になります。
ポイント
地代家賃 1万円 / 現金預金 20万円
事業主貸 19万円
事業主貸とは、事業に関係ない支出を計上するときに利用する勘定科目です。
法人では出てきませんが、個人事業主の方はよく使う勘定科目になるため覚えておきましょう。
自宅が賃貸ではなく、持ち家の場合は何を経費にできる?
自宅が持ち家の場合は、下記のものを家事按分により経費にすることができます。
経費にできるもの
- 建物部分の減価償却費
- 固定資産税
- 住宅ローンの金利部分
なお、建物部分の減価償却費とは、建物の購入代金を法定耐用年数とよばれる資産の寿命のようなもので按分し、月々、一定額を費用として計上しているものになります。
また、マンションの場合には、管理費や共益費も経費にすることができます。
不動産を購入した際の購入代金を丸々、家事按分して経費にすることはできませんし、住宅ローンの元本部分の返済も家事按分の対象にはなりませんので注意してください。
これらはあくまで資産の購入もしくは負債の返済にあたり、費用としての性質のものではないからです。
ちなみに、住宅ローン控除を受けるためには、床面積の2分の1以上が自己の居住用である必要があります。また、事業用割合が10%以下であれば、居住用割合を100%とすることができます。
したがって、この住宅ローン控除の制度を利用する場合は、家事按分で10%を事業用の割合とすることが、一番の節税になる可能性があります。
水道光熱費やその他の生活費も家事按分は様々なところで利用できる!
家賃以外にも以下のような費用を家事按分により経費にすることができます。
家賃以外の経費にできるもの
- 自宅で仕事をしている場合の水道光熱費やインターネット通信費
- プライベート用と事業用の両方で利用している携帯電話の通信費
- プライベートと事業両方で利用している車の駐車場代、車検代、ガソリン代、ETC代、固定資産税
なお、電気代は、使用時間の割合のほかに、コンセントの事業利用の割合などを利用するケースもあります。
家賃の計上タイミングは?計算方法を途中で変更してもいいの?
家賃を経費にするときには、1か月に1回家事按分をし、計上する方法と、年に1回まとめて家賃を計上してしまう方法の2種類が一般的です。
毎月、事業での利用割合がほとんどかわらないような場合には、年に1回まとめて家賃を計上してしまう方が簡単です。
一方で、月によって利用割合が大きく変動する場合には、多少面倒ですが、毎月家事按分を行い、計上する方法の方が無難です。
なお、家賃の計上方法を適宜、使い分けることはできず、原則として、一度決めたらそのルールを変更することはできません。
頻繁にルールを変更して費用を多額に計上していれば税務署に指摘される可能性がありますので、ご注意ください。
家事按分の割合がわからなかったらどうする? 金額の目安は5割程度?
例えば、自宅の色々な箇所を仕事で利用しており、仕事部屋の面積などを利用して簡単に家事按分ができない場合にはどうすればよいのでしょうか?
そんな場合にも、仕事時間の記録をとるなど、様々な方法を吟味し、一定の理屈のつく家事按分方法を決定しなければなりません。
ただ、比較的家事按分の計算根拠が曖昧だと、税務署が入ったら不安だと思うかもしれませんが、目安として、5割程度までは問題ないと考えられているようですので、参考にしてください。
ちなみに家事按分の計算についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご参考ください。
家事按分を利用した場合に、保管しておくべき書類は何?
確定申告の際に、家事按分の算出根拠資料の提出は求められていませんが、根拠資料の保管は義務付けられています。
したがって、家事按分の際に、面積割合を利用した場合には、「自宅兼事務所の間取り図」などを、作業時間の割合を利用した場合には、「作業時間の記録、履歴」などは必ず保管しておくようにしましょう。
おすすめのクラウド型会計ソフト3選
さて、そもそも皆さんは今現在どんな会計ソフトを利用していますか。
クラウド型の会計ソフトを使っていない人がもしいれば、経理の工数が相当減ると思いますので、クラウド型会計ソフトを絶対に導入すべきと断言できます。
また、会計ソフト無しで確定申告しようなんて甘い考えをもっている人も、
「安い」もしくは「無料の」クラウド型会計ソフトを導入して経理の時間削減を絶対にすべきです。
会計ソフトのコストよりも、クラウド型会計ソフトを利用することによる、経理時間や経理コストの削減効果の方が大きいからです。
家事按分もクラウド型会計ソフトであれば自動で仕訳がされるため、非常に楽です。
ちなみに、「安い」もしくは「初年度無料」で機能も充実しているクラウド型会計ソフトは実は3つしかありません。
おすすめの会計ソフト
・freee・・・初心者向け/年間11,760円(税抜)/初月無料
・マネーフォワード・・・経験者向け/年間10,800円(税抜)/初月無料
・やよいオンライン・・・経験者向け/年間8,800円(税抜)/初年度無料
ちなみに、おすすめの会計ソフト、会計アプリの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。
格安で確定申告が可能な税理士
最後に、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。
節税のことや経費のことを自分で勉強するのは結構時間がかかります。
また、確定申告は非常に面倒な作業です。
ですので、「税理士を安くつけることはできないか」と誰もが考えます。
税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、
ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。
そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。
弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。
まだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。
どれだけ自分で税金や経費のことを勉強していても、勘違いしてしまっていることは実は山ほどあります。
税金や経費に関する記事も間違いがよく見受けられます。
そういった勘違いや間違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。
以下の税理士事務所は10万円程度で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。
みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。
ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。
よろしければ、お見積りをとってみてください。
税理士の探し方や各地域でのおすすめ税理士をご紹介
各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。
よろしければ、参考にしてみてください。
-
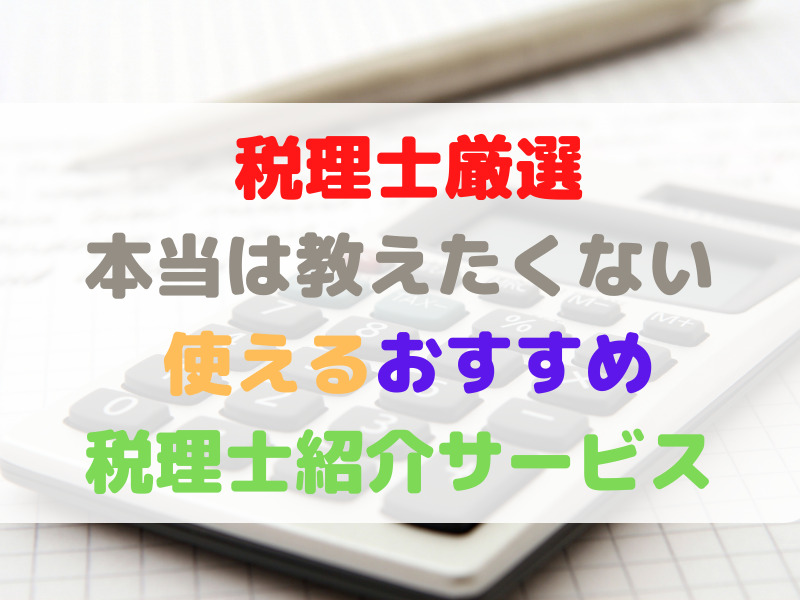
【税理士厳選】評判の良いオススメ税理士紹介サービスランキング8選
-
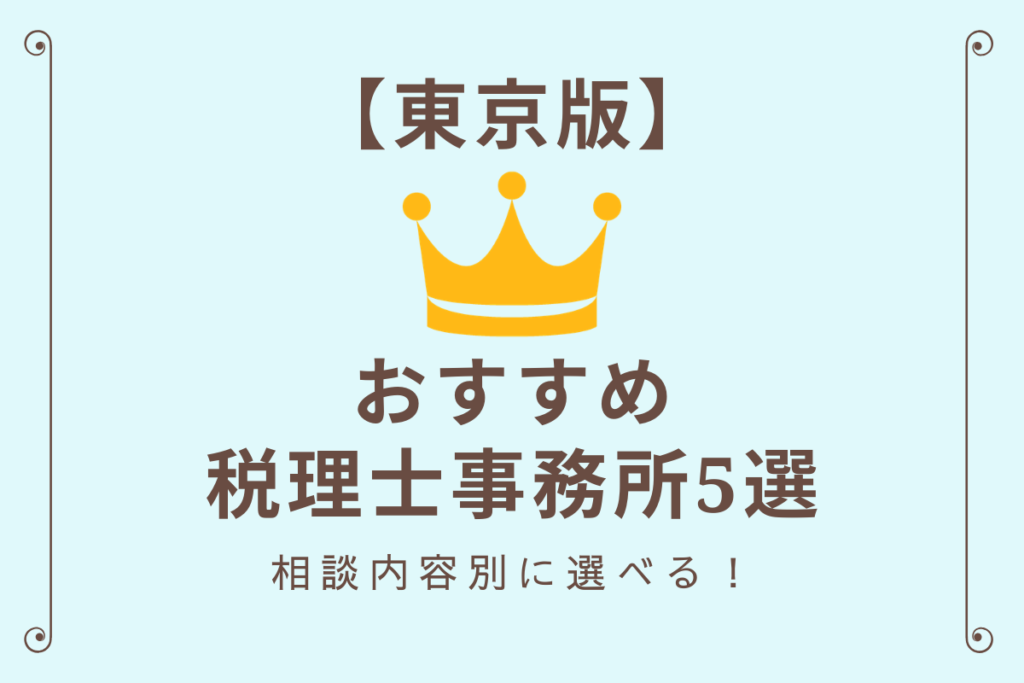
東京でオススメの税理士事務所ランキング5選!相談内容別に解説。一覧から検索、口コミでいい税理士と出会えるのか?
-
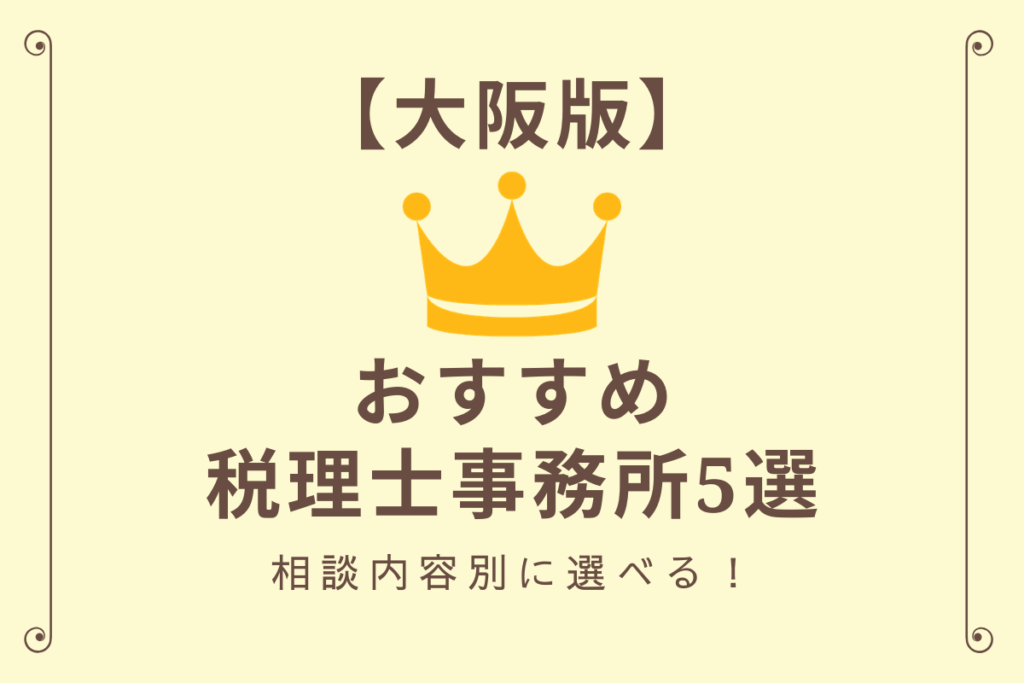
大阪で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告など相談内容別に比較!
-

【2024年】税理士に無料で相談する方法3選【確定申告や相続税申告で困っている方必見】
-
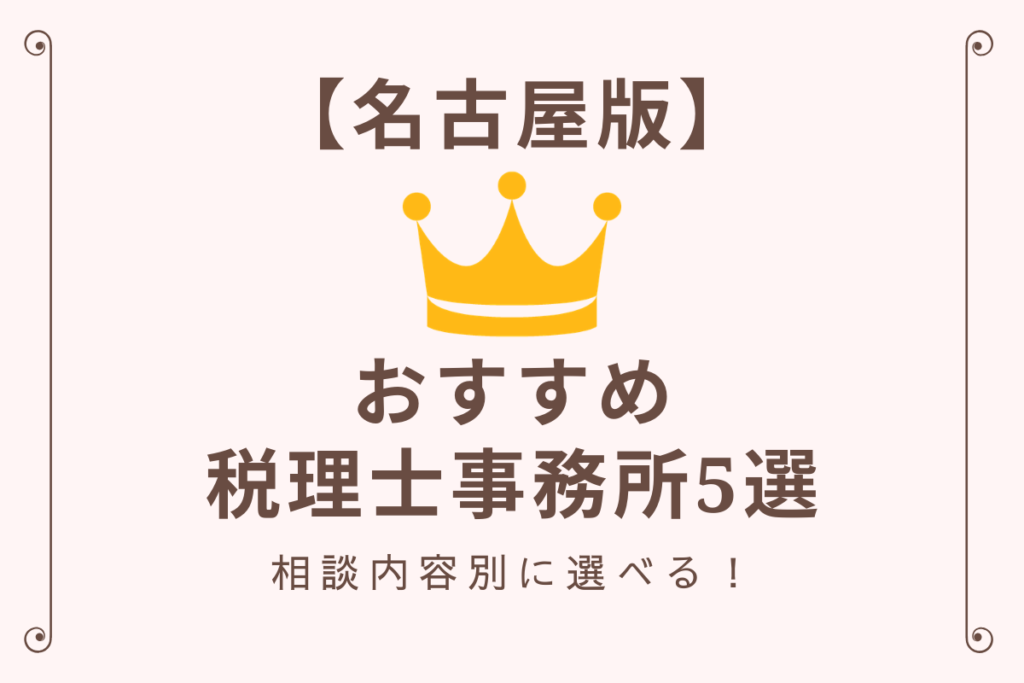
愛知県・名古屋で評判が良い税理士事務所オススメランキング5選!相続や確定申告など相談内容別に解説、比較!
-
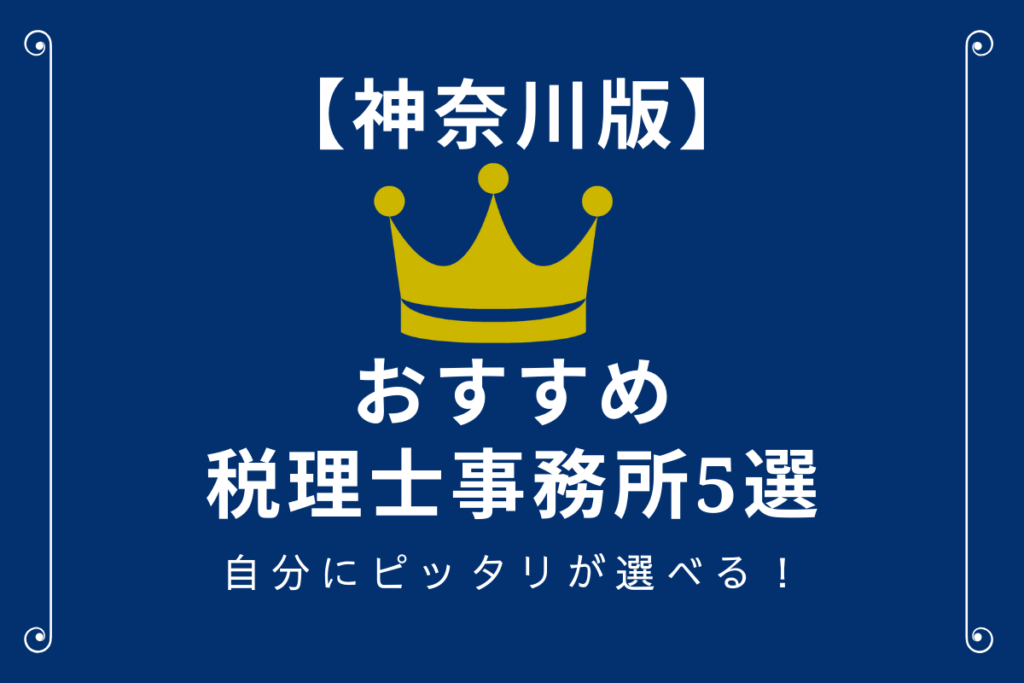
【2024年最新】神奈川県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
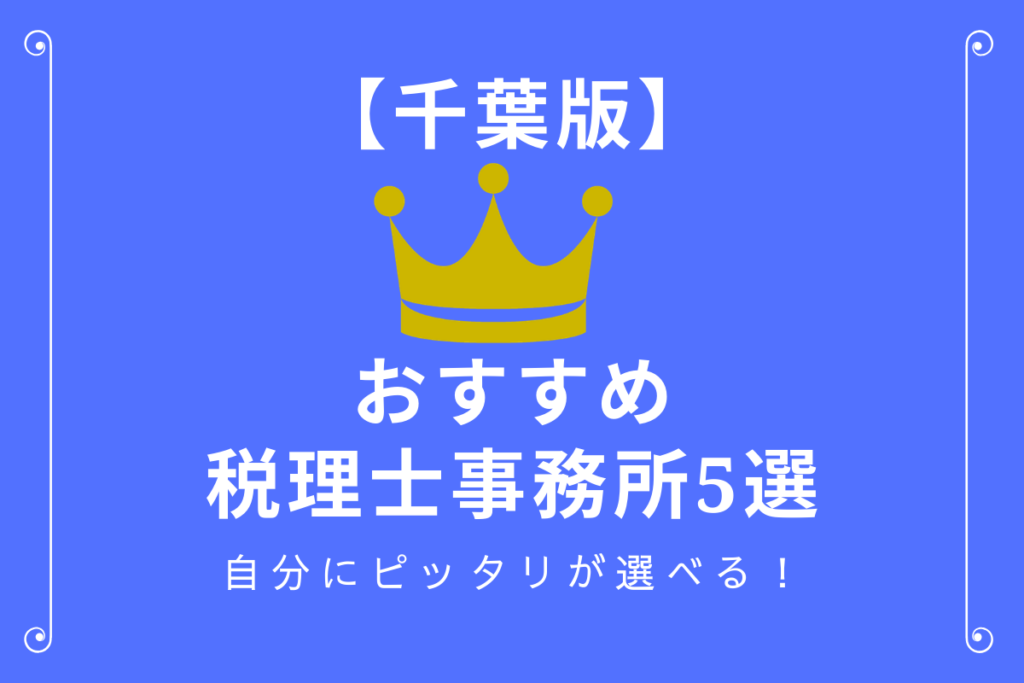
千葉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

福岡県・福岡市で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告など相談内容別に比較、解説
-

兵庫県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

北海道で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

東京都世田谷区で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
まとめ
自宅の家賃を経費にすることは、個人事業主の経費を利用した節税の第一歩です。家事按分をしっかりと理解して、自宅の家賃だけでなく、経費を漏れなく計上し、節税に役立てましょう。